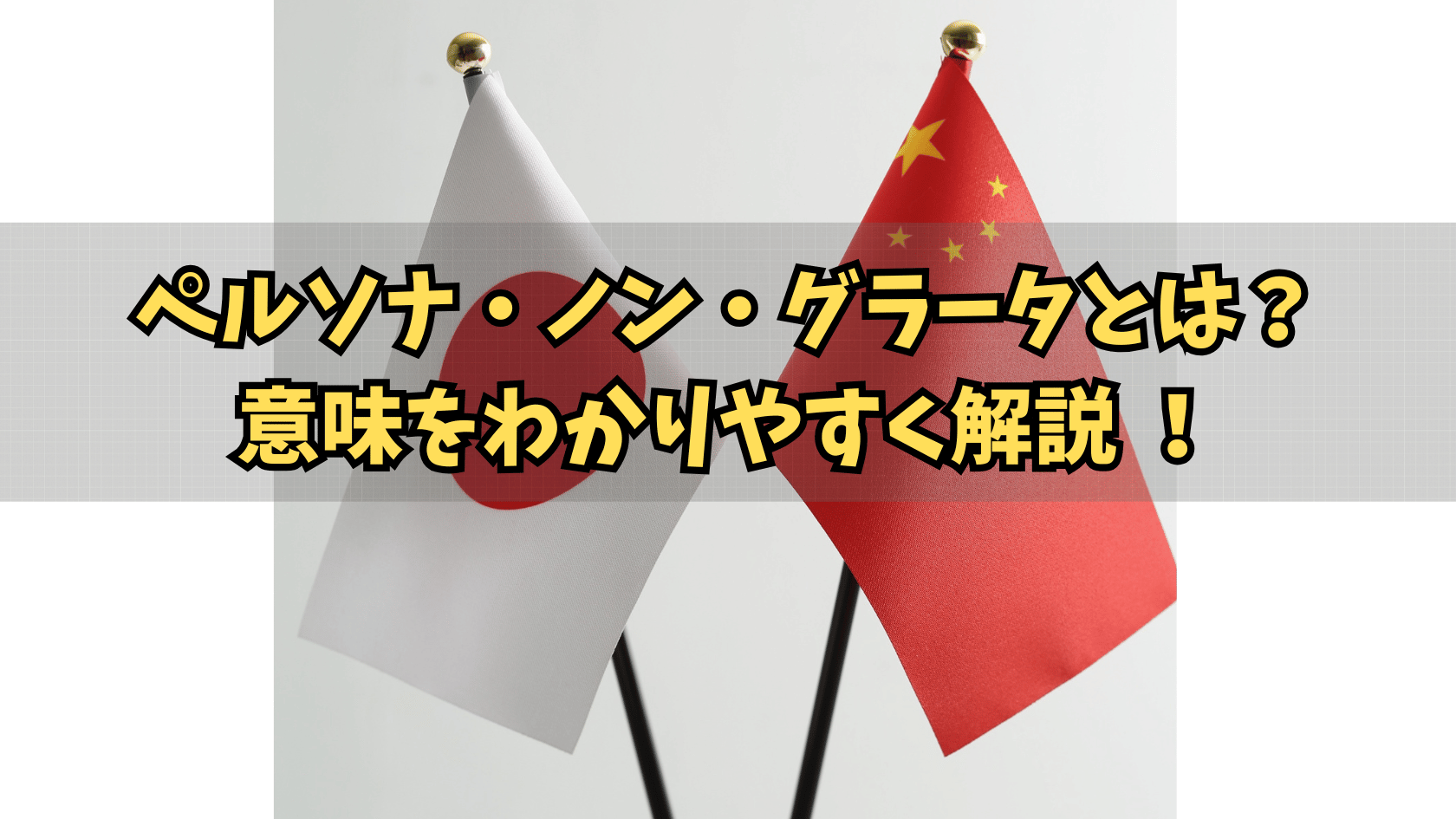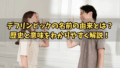先日、駐大阪中国総領事が、高市早苗首相の台湾有事に関する国会答弁へ反応し、X(旧Twitter)に強い表現を用いた投稿をおこなったことが大きな話題となりました。
この投稿は日本国内でも「外交官として不適切ではないか」「日本に対する侮辱ではないか」と批判が広がり、与党内からも政府へ厳しい対応を求める声が上がっています。
#自由民主先出し
— 自民党広報 (@jimin_koho) November 11, 2025
📌ペルソナ・ノン・グラータを含めた対応を行使するべき
中国の総領事の不適切投稿を受けて決議を採択…
その議論の中で特に注目されているのが、外務省や国際ニュースでしばしば言及される 「ペルソナ・ノン・グラータ(persona non grata)」 という専門用語です。
普段の生活では滅多に聞かない言葉であるため、SNSでは「どういう意味?」「追放ってこと?」「一般人にも適用できるの?」といった疑問が多く見られます。
今回のニュースは、この「ペルソナ・ノン・グラータ」という言葉を知るうえで非常にわかりやすい事例となっており、外交上どのように使われるのか、どんな効果を持つのかを理解する良いきっかけとなっています。
この記事では、
・ペルソナ・ノン・グラータとは何か
・なぜ外交問題でよく出てくるのか
・今回のニュースとどう関係するのか
を中心に、専門知識がなくても理解できるようにわかりやすく解説していきます。
※この記事にはPRが含まれています。
「ペルソナ・ノン・グラータ」とは — 意味をわかりやすく

「ペルソナ・ノン・グラータ(persona non grata)」は、ラテン語で直訳すれば「歓迎されない人物」「受け入れ難い人物」という意味です。
外交用語として使われる場合には、ある国(受入国)が、他国から派遣された特定の外交官(もしくは外交使節団の構成員)を「この国ではもはや受け入れられない」と宣言し、その外交官に対して国外退去を求める制度を指します。
具体的には、「受入国は理由を説明せずに、いつでもその外交官をペルソナ・ノン・グラータと宣言できる」という国際条約上の仕組みがあります。
その結果、宣言を受けた外交官は、その国での任務を終え、通常本国に召還されるか国外退去となります。
国際法上の根拠と手続き(ウィーン条約の仕組み)
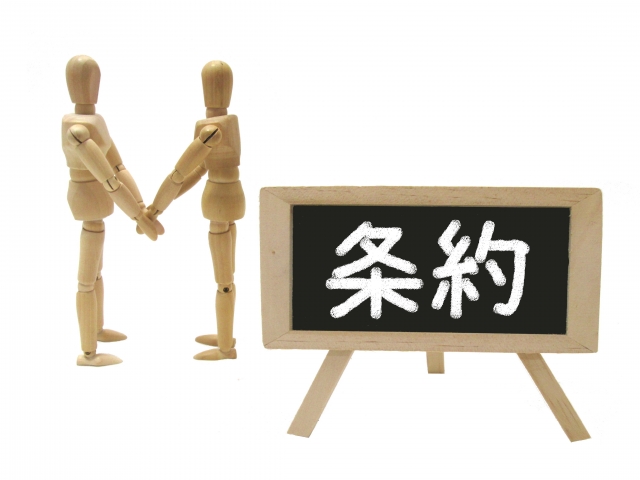
この制度の根拠は、たとえばウィーン条約(外交関係)およびウィーン条約(領事関係)にあります。
これら条約では、受入国が「アグレマン(agreement、承認)」を与えた上で外交官が派遣されることなどが規定されており、アグレマンを取り消す手段としてペルソナ・ノン・グラータの宣言が認められています。
具体的な手続きとしては、受入国の外務省等を通じて「あなたはこの国に駐在する外交官として受け入れられないので、合理的な期間内に出国してください」と通告されるケースが典型です。
また、重要なポイントとして、受入国は理由を説明する義務がないとされており、宣言が出された後は、該当外交官が拘束された場合、外交特権が適用されず一般市民扱いになる可能性もあります。
過去の事例(日本や他国の追放・応酬)

過去には、たとえば2022年、ウクライナ侵攻を受けて、欧米各国がロシアの外交官を次々とペルソナ・ノン・グラータとして国外退去させた事例があります。
日本でも2022年10月、ロシアの外交官が「スパイ活動疑惑」で国外退去処分となったことが報じられています。
こうした事例から、外交関係における応酬(追放→追放)という構図が常套手段となっています。
また、今回のように外交官の発言や行動が「内政干渉」「暴言・脅迫」と受け取られた場合、PNG指定のハードルが下がるという指摘も専門家から出ています。
今回のケースであり得る展開(外務省対応・外交的報復の可能性)

今回、駐大阪総領事・薛剣氏の投稿は「日本の首相を対象とした脅迫ともとれる発言」であり、専門家の間でも「もし米国なら即刻国外退去だ」との声が出ています。
日本政府・与党では、「投稿が極めて不適切である」「ペルソナ・ノン・グラータを含めた毅然とした対応を政府に求める」との声が出ており、今後、次の選択肢が考えられます。
- 対応A:抗議にとどめる。声明発表・中国側に説明を要求し、追放には至らない。これが最もソフトな対応。
- 対応B:PNG指定として追放を実施。駐大阪総領事を日本から帰国させる。国際的にも強いメッセージとなる。
- 対応C:派遣国(中国側)が報復措置を取る。例えば日本駐在の中国外交官を追放する、あるいは経済・人的交流に制限を設ける。応酬関係が悪化する。
ただし、日本政府がB案を取る場合、日中関係の経済的・人的関係への影響、さらには台湾有事を巡る安全保障リスクなども総合的に判断する必要があります。
専門家のあいだでも「中国側が絶対に謝れない国内事情」が強硬策を難しくしていると指摘されています。
一般人の「出禁」との違い(混同しやすい点を整理)
「ペルソナ・ノン・グラータ」が一般的な「出禁」「出入禁止」「悪言を吐いたので社交界から追放された」という比喩と異なる点を整理します。
| 項目 | PNG(外交) | 出禁/比喩的使用 |
|---|---|---|
| 対象 | 外交官・使節団構成員(国際法対象) | 一般人・団体・個人(私的・比喩的) |
| 根拠 | 国際条約(ウィーン条約等) | 社会通念・契約・団体規則など |
| 効力 | 正式に国外退去させることが可能 | 法的拘束力が弱く、主に社会的制裁 |
| 理由説明 | 原則不要 | 多くの場合、理由を説明する |
| 再任・再登場 | 実質的に難しい場合あり | 状況次第で再び登場可 |
👉「PNG」は国際法上の制度であり、比喩的に使われる「出禁」とは質が異なります。
よくあるQ&A
Q1:PNG指定に際して理由を出さなければいけない?
A:いいえ。受入国は「理由を説明せずに」PNGと宣言できます。
Q2:PNG指定された外交官は二度とその国に戻れない?
A:原則として、その国での任務継続はできませんが、外交関係が変われば再任の可能性も理論的にはあります。
Q3:一般の外国人にこの制度は使える?
A:いいえ。この制度は外交関係・領事関係に関しており、一般の在留外国人や旅行者には適用されません。
まとめ:今回のニュースで私たちが注目すべきポイント
今回の駐大阪総領事・薛剣氏の投稿は、「国家元首的地位の人物への脅迫とも受け取れる内容」であり、外交界における大きな問題を含んでいます。
今後、日本政府が「ペルソナ・ノン・グラータ」指定を行うかどうか、その判断基準・タイミング、さらにはそれを契機に日中関係がどう動くかが注目です。
また、この機会に「ペルソナ・ノン・グラータ」という外交用語の意味・仕組みを整理しておくことは、国際ニュースを理解するうえで非常に有効です。
外交官の発言一つが国家関係に波紋を広げる時代、私たちも“言葉の背景”を知ることが重要といえるでしょう。